探究活動とは
探究活動は「生きる力」をつける方法として注目されている学習形態です。
上手く活動ができれば普段の座学とは違う能力を身につけることが可能ですが、生徒側はもちろん、指導者側もどのように進めていけば良いのかが手探りな状態です。
それは当然で、探究活動が注目されたのは近年のことで、指導方法が確立されていないからです。
また、自身が生徒だった時に探究活動を行った人は僅かで、理数科などの専門科などごく一部以外の人には馴染みのないものです。
5年間の探究活動の指導を行い、自分なりのフォーマットを作成できたので時系列と共に紹介したいと思います。
探究活動の流れ
授業で探究活動を行う際の年間予定を目安として作成しました。以下の全9項目です。
- 授業前準備①年間予定とルールの設定
・各発表の日時と場所の決定
・ルールと条件の設定
・提出書類のフォーマット作成
・予算の確認 - 初回授業②シラバスの確認とアンケート実施
・授業の目標の説明
・①での決まり事の共有
・班分けに関するアンケートの実施 - 授業2回目前③班分け
・探究のジャンルごとに班分け
- 授業2回目④テーマ設定
・班ごとに探究テーマを設定
- 授業3回目以降⑤探究活動開始
・テーマが決まり次第探究開始
・レポートと発表用スライドの説明と確認 - 7〜8月⑥中間発表/中間評価
・事前に提出させたレポートを全員に配布
・班ごとにそれまでの活動をまとめて発表会を行う
・評価アンケートの記入後、集計し各班に配布
・これからの方向性を確認し、探究再開 - 11〜12月⑥´中間発表/中間評価
・事前に提出させたレポートを全員に配布
・班ごとにそれまでの活動をまとめて発表会を行う
・評価アンケートの記入後、集計し各班に配布
・これからの方向性を確認し、探究再開 - 1〜2月⑦最終発表
・事前に提出させたレポートを全員に配布
・担当職員以外も観客に呼んで発表会を行う
・評価アンケートの記入 - 発表後⑧総括、冊子の作成
・評価アンケートを集計、各班に配布
・各班でレポートと発表用スライドを加工して冊子の原稿を作成し、まとめる
・全体の活動について講評を行う
今回は①について解説します。
②〜⑧の各項目に関して次回以降1つずつ解説していきます。
年間予定とルールの設定
まず、担当教員として最初に考えることはスケジュールを押さえることです。
確認するべきことは次の5つです。
- 中間発表の回数
- 各発表の日時と会場
- 何班に分けるのか
- 提出書類と期限の設定
- 予算の確認
この他には、担当教員が一人なのか複数人体制なのかで変わりますが、
複数人体制の場合は、アンケートの集計の当番など共通する事務作業を分担すると良いでしょう。
中間発表の回数
成績をつける関係で、各学期に1回は発表の場を設けるのが望ましいと思います。
そのため、中間発表は夏休み前と冬休み前の2回。最後に本番の発表を行うのが理想です。
また、中間発表を2回用意することで発表の練習回数が確保できます。
他の班の発表の様子を2回見ることができることと、提出書類を段階ごとに作ることができるのもメリットです。
中間発表がないと、いきなり提出物全てを年度末に出し、ぶっつけ本番のような発表を終えて探究活動が終わってしまいます。
生徒の探究活動に対する緊張感を適度に持たせることと、一回ごとの負担軽減、より深い探究活動を行うためにも複数回の発表の場を設定するのが良いでしょう。
ただし、授業の単位数が1で毎週1回の授業しか行えない場合は、中間発表の持ち時間を本番よりも短くするなどの工夫が必要かもしれません。
各発表の日時と会場
日時に関しては、学校の年間行事予定と成績の締め切りを考慮して設定しましょう。
目安としては成績の締め切りの1週間前にはそれぞれの発表を済ませておきたいところです。
最終発表の後に、評価の確認と成果物のまとめとして冊子の作成を行いたいので、1〜2コマ分は授業時間を確保しておくことが望ましいです。
また、複数名で授業を行う場合は、出張などが無く全員が見れる時間かどうかを確認する必要があります。
1つの班の発表時間も設定しましょう。
一般的な目安としては質疑応答込みで各班10〜15分は欲しいところです。
その他に、司会の説明、各班の発表時間、校長などの講評、アンケートの記入時間。
これらの時間を発表会の所要時間として考慮する必要があります。
口座の人数と班数によって状況は変わりますが、班数が多く時間がギリギリになってしまう場合は、最終発表の時だけは授業交換を行なうなど、連続で2コマ確保すると慌ただしくならずに済みます。
次に会場に関してです。
中間発表に関しては、普段の授業で使う教室でもいいですが、本番と同じ会場が使えるなら機材の設定も練習できるので、同じ環境で行うのが望ましいです。
普段とは違う会場で行うことで緊張感が高まり、良い発表練習になります。
そのため、会議室などのICT機器も使える会場を押さえておきましょう。
また、最終発表に関しては、なるべく多くの先生等の観客の前で発表することが望ましいです。
可能であれば他の授業をもらって、クラスや講座や学年などが異なる様々な生徒の前で発表できると刺激になって尚良いです。次の学年の参考にもなるので、学校としてもいい影響を与えることが期待できます。
急には講座や学年を跨ぐことはできないので、そういった計画や相談を学年や管理職などと相談しておくと良いでしょう。
何班に分けるのか
基本としては人数が均等になるように分配して班を構成するのが望ましいです。
生徒が20人いる場合は5人ずつの4班が良いでしょう。4班であれば各班の発表の持ち時間を10分にすることで、最終発表を50分1コマの中に収めることができるからです。
これよりも班数を絞る場合は6人以上の班が出てくることになります。班員が多苦ても探究活動は成立しますが、上手く役割分担をしないと暇を持て余す班員が出てきてしまう可能性があります。そのため、多くても5人までにした方が無難です。
また、これよりも班数を増やす場合は5班以上あると最終発表での各班び持ち時間が10分を切ってしまいます。そのため、発表時間が少なく忙しない発表会になってしまいます。5班以上の場合は思い切って最終発表を2コマで行う必要があるでしょう。
そのほかに、班内に役割分担を決めておくのも良いかもしれません。班長、副班長、データ処理係、スライド作成係などを設定するとそれぞれの責任感が生まれるでしょう。
あらかじめ教員側が設定してもいいですし、各班の自主性に任せてそれぞれの係を作らせてもいいかもしれません。
提出書類と期限の設定
次に確認するのは提出物とその期限です。
探究活動を授業で行うにあたって、他者から見て何を探究したか分かるような成果物が必要になります。また、次年度以降に伝える資料にもなるのでレポートを作成するのが良いでしょう。
進学する場合は卒論にもつながる部分があるので、論文を見据えた練習としても有意義だと思います。
レポートを課す場合は、フォーマットを配布するとスムーズです。
フォーマットを用意しないと何を書けば良いのか分からなくなってしまいます。各班ごとに任せてしまうと統一感が無く、書く内容がまちまちになってしまうからです。
レポートの項目としては、
- はじめに
- 探究方法
- 探究結果
- おわりに
の4つを基本として、あらかじめいつまでに完成させるのかの日程を記入しておくとわかりやすくて良いでしょう。例えば、探究方法に関しては「1回目の発表までに記入し、印刷できる状態まで進めておく」といったように期限を決めておくと良いでしょう。
そして、次の2回目の発表ではその時の研究結果をまとめておき、今後の展望について中間発表で紹介することで、少しずつ試行錯誤しながら完成に近づけることができます。
最後の発表前に「おわりに」まで書いて完成、というような流れになります。
締め切りを設定しておくことで、本番直前で慌てることなく発表の準備に専念ができるようになるでしょう。
また、レポートの書き方を指定しておくとスムーズに活動が進みます。
書き方はPREP法で知られている書き方が良いでしょう。
PREP法を簡単に説明すると、Point(結論)、Reason(理由)、Example(例)、Point(結論)の順で述べる文章作成方法のことです。
最初に結論を書きその後にその説明を足していき、最後にまとめとして結論を再確認するので、書きやすく、分かりやすい文章になります。大学に進学した際の論文作成でもこのやり方はよく使われているので、今のうちから慣れておくと生徒にとってプラスになるはずです。また、面接時でも主張がブレにくいので習得しておくと良いことを伝えると良いかもしれません。
そして、文体の指導も合わせて行うと良いでしょう。
「ですます調」の敬体でまとめるのか、「である調」の常体でまとめるのかを統一しておきましょう。これは就職や進学時の書類作成でも役に立ちます。
次に発表用スライドの作成についてです。
スライドを作るにあたって1番気をつけなければいけない事は、1つのスライドに情報を詰め込みすぎないと言うことです。
発表というものは「相手に伝わるか」が最も重要です。
そのため、スライドの中に原稿を全て詰め込んだような資料は不適切です。
また、発表用のスライドを検索すると、自治体や政府が作成しているような物が見つかりますが、こういったスライドは発表用のスライドと配布用の資料を兼ねている場合がほとんどです。
そのため、発表の場にいない人や、後から資料として読んだ時に、そのスライドから全ての情報を取得できるように作られています。
これは探究活動の発表で作成するべきスライドと目的が180度違っています。
もしすべての情報をスライドに詰め込んだのであれば、それを配布するだけで事足りるからです。
あくまでもプレゼンテーションなのでただ書いてあることを読むだけでは意味がありません。
スライドは情報を詰め込みすぎずに箇条書きのようにキーワードをまとめるに留め、内容や補足に関して口頭で説明するのが理想的です。
スライドに文字が多い場合は観衆は文字を読むのに精一杯になってしまって、発表者の発言をしっかりと聞く余裕がなくなってしまいます。また、すべての説明がスライド上に記載されているのであれば発表を聞く必要がそもそもないので無駄な時間を過ごすことになってしまいます。
せっかく発表者と参加者の時間を使っているので、その場にいるからこそ伝わるプレゼンテーションを行うのが良いでしょう。単調な説明にならないように工夫を凝らして発表用のスライドや資料を作成するということを共有しておきましょう。
発表に関する詳しい話については発表が近づいてきたら話をするという形で対応するのが良いでしょう。最初は探究活動が進んでいないので何もまとめる資料がありません。そのため、ある程度探究活動が進みまとめる資料が増えてきた時に話すのがイメージが湧きやすくて良いと思います。
予算の確認
最後に確認しておきたいのが授業で使える予算の話です。
教材費としていくら使えるのかを把握しておくことで、最後の達成感が変わってきます。
具体的には探究活動の成果物として、最後に冊子を発行したいので、それを作るための色紙と製本テープ代を教材費として用意しておきたいところです。
この他に、学校側からの予算がつくのなら、班の数分のUSBメモリーと探究活動用にホワイトボードや発表時に使うマウス機能を持つポインターなどがあるとより本格的な活動になるでしょう。


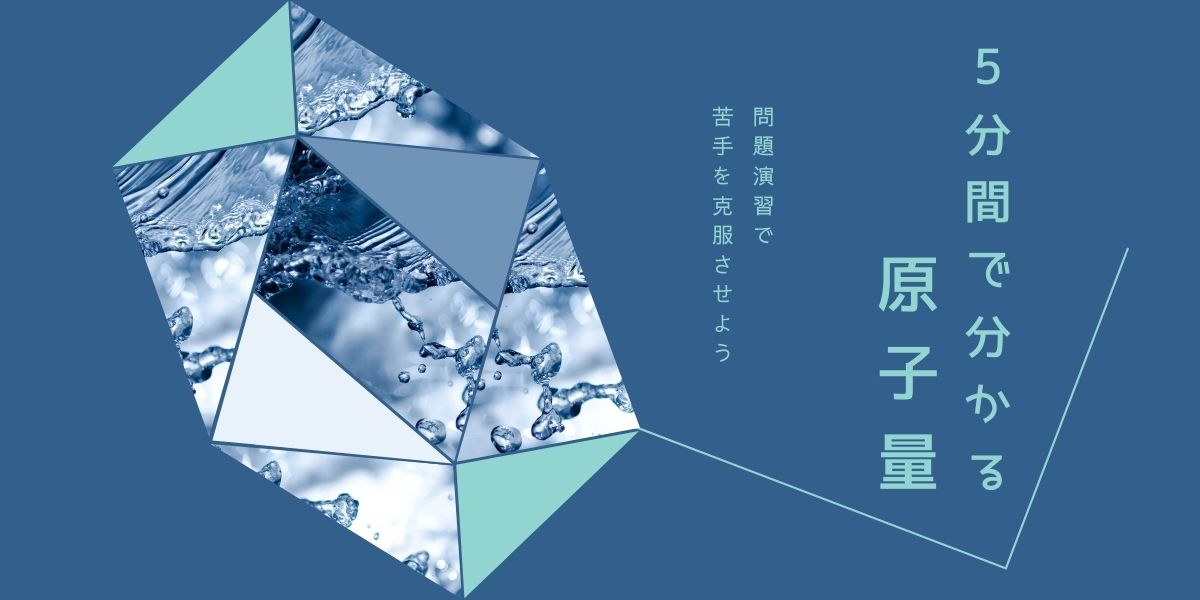
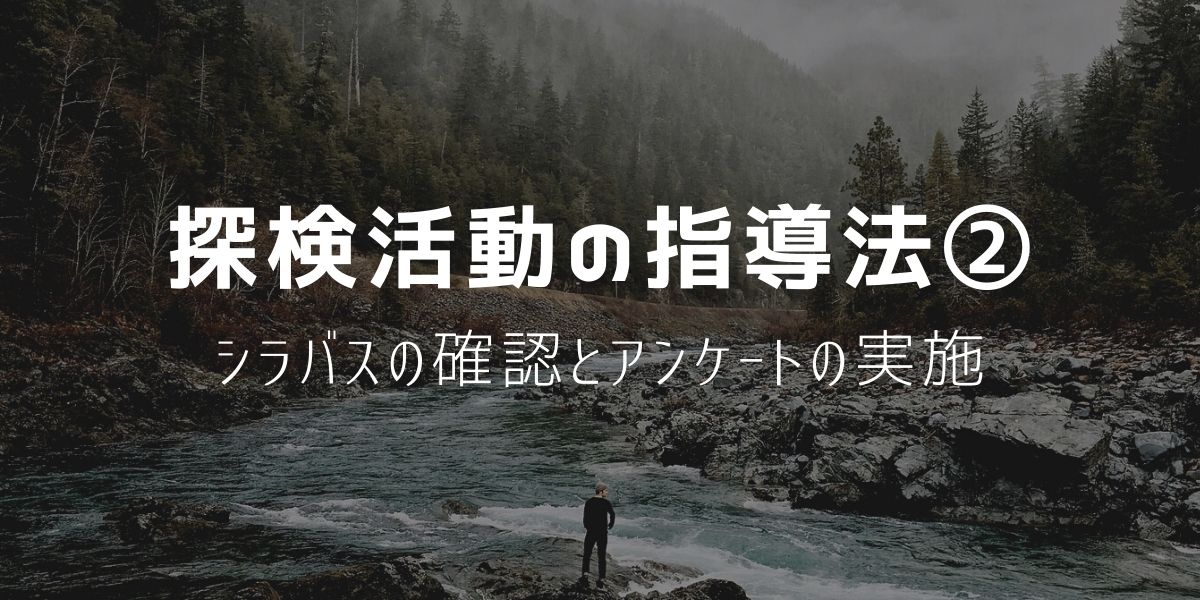
コメント